
CEOとCOOが語る、Rehabの成長と創造するべき「未来」について(前編)
こんにちは! 株式会社Rehab for JAPAN 採用担当です!
今回はCEO大久保とCOO池上による対談インタビューとなります。二人の対談は、さかのぼること2023年2月公開以来(当時の記事はこちら)。その当時のリハブからどのような変化や成長を遂げたのか、また今後リハブが目指していることや創造したい未来など、ざっくばらんに語ってもらいました。

右:COO 池上
Rehabの本質は、リハビリ支援にある。
―― まずはここ2~3年をふり返ったときに、リハプランだけだったプロダクトが「Rehab Cloud 〇〇〇」としてマルチプロダクト化してきました。このサービス拡張にはどのような狙いがあったのでしょうか?
池上
2018年にリハプランをローンチしてから約7年経ち、累計導入事業所は2800事業所以上と、本当に多くのお客様にご利用いただけるサービスに成長してきました。デイサービスにおける自立支援や重度化防止は「介護の一丁目一番地」だと捉え、個別機能訓練計画やLIFE提出などの「リハビリ支援」を中心に、介護現場職員や利用者のことを第一に考えたプロダクトづくりを行ってきました。
手前味噌ですが、デイサービスのリハビリ支援に関しては圧倒的な優位性を持ったソフトウェアだという自負があります。
しかしながら、現場の生産性を上げてケアの質を向上させるていく上で、リハビリ業務だけでなく介護現場の業務全体の体験設計が必要があり、そのために必要なプロダクトが増えていったという経緯です。
大久保
もちろん、記録アプリ「Rehab Cloud デイリー」や、AI動作解析ソフト「Rehab Cloud モーションAI」も、とにかく高齢者を元気にしたい、自立支援を広めていきたいという想いから生まれたサービスですが、リハプランは、創業当時からの想いが最も乗っかっています。それを広めるために何が必要かを考えたとき、やっぱり請求ソフトである「Rehab Cloud レセプト」の開発着手に至ったわけです。
池上
そもそも介護事業所は、必ず国保連への請求業務という作業があって、毎月必ず利用者への提供実績を入力し、売上実績となる保険点数を計算するプロセスがあります。その作業のために、ほぼすべての介護事業所は請求ソフト(レセプト)と呼ばれるソフトウェアを活用しています。そんな中で、すでに事業所内で使われている請求ソフトとは別に、当社のようなリハビリ支援ソフトを導入すること自体が負担となってしまうケースがあるんです。あまりITに強くない介護現場において、2つのソフトウェアを二重で管理運用することの煩雑さが新たな課題となり、導入を躊躇されることも少なからずありました。
大久保
お客様から、自立支援やリハビリの強化も必要だし、リハプランの価値を理解し、導入したいと思っていただけたにもかかわらず、この請求業務部分の機能を有していないことで泣く泣く導入できないとお断りされる。そんな課題を乗り越えるために、レセプトを開発し、我々がお客様をサポートできる範囲を広げていこう、という判断になったわけです。

―― それでは、会社としても念願のプロダクトだったんですね。
池上
開発当事者の心理で話せば、おっしゃるように念願のプロダクトだと言えます。ビジネス的な観点でも強いフックになります。でも、だからといって自分たちが “レセプト屋さん” になったつもりは、まったくないんです。
大久保
そこは誤解なく伝えたいですよね。僕からも補足をすると、既存の介護ソフトって「経営支援」とか「開業支援」を軸に展開されてきた製品がほとんどで、経営者の課題解決にフォーカスされています。でも私たちは、あくまでも現場で働く介護職員と利用者に向き合っています。入力確認作業などの間接業務を効率化した結果、どれだけ高齢者を元気にするために向き合う状況をつくれるか。つまり「Rehab Cloud レセプト」は請求ソフトであっても「自立支援」「科学的介護」を推進するためのアプローチのひとつであり、既存のレセプトとはそもそも設計思想が違います。
池上
実際、僕らも事業所の方と直接お会いする機会がありますが、皆さん高齢者を元気にしたいという思いを強く持っていらっしゃいますし、利用者さんと向き合う仕事に専念したいと思っている方ばかりです。けれどその一方で、紙帳票や紙台帳の記録を請求ソフトへ転記する作業などに時間が割かれてしまっていて、利用者さんと向き合う時間を確保できなかったり残業が増えたり、場合によって離職の原因になっていたりもします。
大久保
本来あるべき役割を担えるデイサービスが社会に増えていってほしい。そのための支援を自分たちの力で成し遂げていきたいと思っているんです。
根強い紙文化とレガシーなソフト。
―― 今の話で気になったのは、既存の請求ソフトの使い方の難しさという点なんですが、その原因として考えられることは何でしょうか?
池上
請求ソフトが登場したのは、介護保険法が制定された2000年前後のタイミング。その当時につくられたシステムに3年ごとに改修を繰り返しながら今に至るソフトなんですよね。介護保険法の難しさもあいまって、新しくつくり替えるのは容易でない。手直し手直しでやるしかなかったという状況もあると思いますが、現場目線で実際にさわってみると、操作の難しさは明白でした。操作する人の体験設計、いわゆるUI/UX、UXデザインみたいな部分が欠落しているというか、本来業務をスムーズにするためにテクノロジーはあるのに、むしろ介護職員の業務を圧迫していないか…? そう思わざるをえなかったです。
大久保
ここ数年で世の中に多くのテクノロジーやAIが登場して、産業としてのDX化が進んでいます。その一方で介護業界では、業務を進化させる余地がまだまだ十分にある印象があります。
池上
似た領域だと医療のほうが、DX化は進んでいる気はしますよね。
大久保
我々もまだまだ進化が足りてないなと思います。というのも、とある事業所の話ですが、そこではタブレットでリハプランを使って記録をしつつも、それをさらに紙に転記していて…。ソフトウェアを導入しても、まだ紙で記録を残す習慣が残ってたんです。
池上
やっぱり紙文化は、まだまだ根強いと感じます。ただ、従事者のITリテラシーの低さにあるのではなく、「当事者たちが当たり前だと感じている環境」をリプレイスできるような業務体験を提供するプロダクトの必要性を改めて感じますね。
大久保
これって提供する自分たちの課題でもあると同時に、事業所が時代に合わせて乗り越えなきゃいけない課題でもあると痛感しました。そもそも現場の1日って、あたりまえだけど機能訓練だけじゃない。介護・介助もしているし、日々の記録もしているし、送迎もやっている。そんな日々の中で定期的に請求業務がある。これらの業務をぶつ切りにしないサービスじゃないと、サービスの良さを実感する前に「なんだか使えないなぁ」という感触が残って、古い習慣が残り続けてしまうんだなぁと。
池上
今の請求ソフトが何となく通用しているのも、長年の習慣によるかもしれないね。だからこそ、本当の意味で一気通貫・一元管理できるソフトを提供したい。自分たちの技術力なら、もっと現場に喜んでもらえるソフトがつくれるはず。そんな思いでレセプト開発は進んでいったプロジェクトです。

あまりの難しさに、スタートアップ向きじゃないと思った。
―― レセプト開発に関しては、在籍するエンジニアのインタビューからも相当難易度が高いプロジェクトだと理解しているのですが、経営者としての葛藤や苦悩もあったと思います。
池上
そうですね。「つくるぞ!」と意気込んだものの「なめてたわ…」と何度もくじけそうになりました。
大久保
特にリリース時点から品質にもこだわったので、どうしても時間はかかりましたね。
池上
たとえばビジネスの都合だけで言えば、もっとスピード優先で中途半端な機能でもリリースして「うちもレセプトもあります!」という状態を確保して、営業活動をすすめ、段階的に改良を加えていく、という方法もあるにはありました。でもそのあたりはCPOの若林とも話をしながら「自分たちは後発でリリースする立場。だからこそ介護現場が劇的に変わる体験を提供できるものをつくろう」ということにこだわりました。
大久保
請求ソフトって、請求金額を計算し事業所の売上を算出するソフトなので、正しく計算できることは大前提として必要です。中途半端にリリースして徐々にアップデートしていくってことじゃなくて、最初からある程度完成したものを用意しなきゃいけないんですよね。
池上
その最低限でもある「正しく計算できる」というレベルにすることが、介護保険制度や自治体ごとのルール、高齢者の属性によってかなり複雑怪奇なものになっていて、設計図をつくるだけでも難易度が高かった。あまりに難しくて、スタートアップ向きじゃないと思ったくらいです。その難解さは話しきれないのでここでは割愛しますが、株主の皆さんには、いかに難しいことにチャレンジしていて、そのチャレンジに意義があるかを真摯に丁寧に説明していきました。
大久保
株主の皆さんは業界理解の深い方ばかりで、開発の大変さを素直に受け止めてくださいました。急かされるようなことはありませんでしたが「本当につくりきれるの?」「既存の企業と提携するような選択肢はないの?」といった声をいただいたりもしました。結果的には、大きな期待をこめて自分たちを待ってくれて、それは、ものすごくありがたかったです。
池上
実際のところ、理想と現実の中で初期リリースの時点での機能装備を諦めた部分もたくさんあります。それらはリリース後の二次ステップとしてアップデートを繰り返していて、現在もよりよいプロダクトにするべく開発は進行中です。
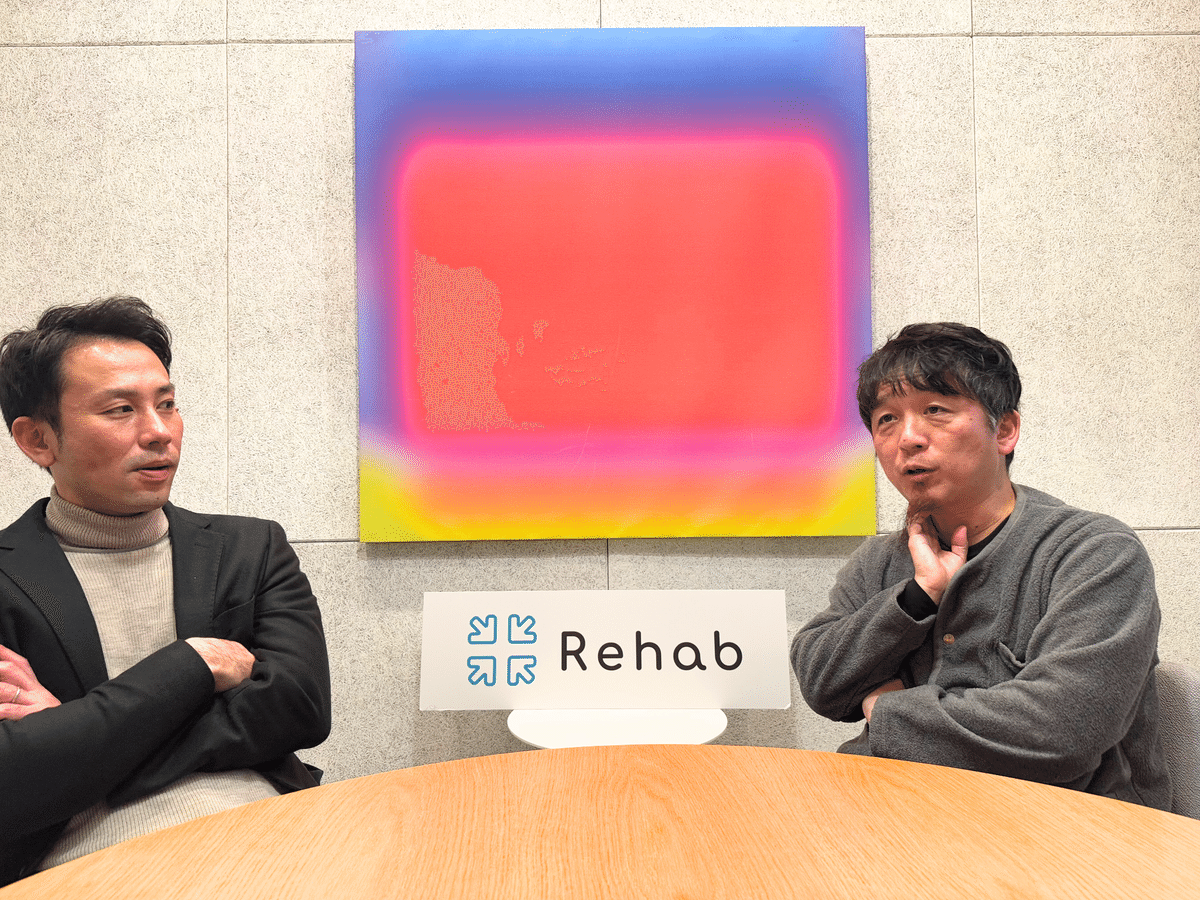
感謝と責任を感じながら、目指す世界を実現したい。
―― 今後の思いや展望を教えてください。
池上
開発に苦戦しているときに「Rehabが変えられなければ、介護業界は誰も変えることができないと思っている」というお声を株主の方からいただくことがあって、すごく励みになったし背筋が伸びる思いにもなりました。引き続きRehabが掲げるビジョンに向けて邁進していきたいです。
大久保
壮大なビジョンを掲げることだけなら、誰でもできると思うんです。それだけではなく、ビジョンの実現に向けて我々がやってきたことの実績や、Rehabが描く成長ストーリーや目指している世界観に対する解像度の高さに納得、共感していただける方々に恵まれて今に至っています。
池上
目指す世界の実現に向けて、どうやって未来の山登りをしていくの? という問いに対しては、かなり高い解像度で挑んでいる自負はあります。登るべき山は、どこで、どんな高さで、どんな距離があって、いつまでに登り切れるのか。右から登ると決めたのはなぜか。それらを徹底的に考え尽くし、説明できるようにしています。
大久保
その通りに行けないこともあるし考えながら動く局面もありますが、多くの人たちの期待に対する「感謝と責任」を強く感じながら、ビジョンの達成に向けて突き進んでいきます。
(後編へ続く)
株式会社Rehab for JAPANでは一緒に働く仲間を募集しています🌈

